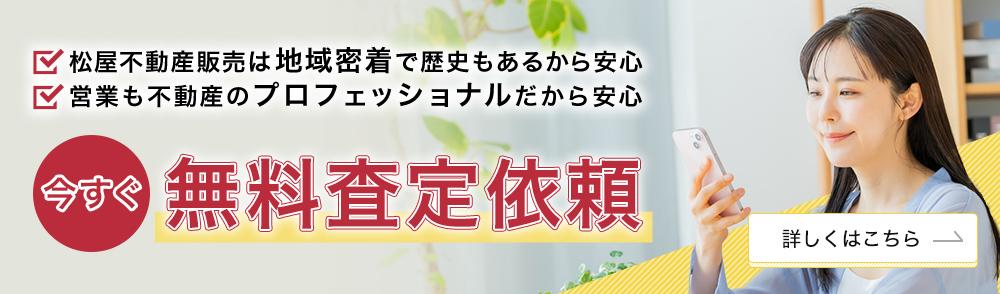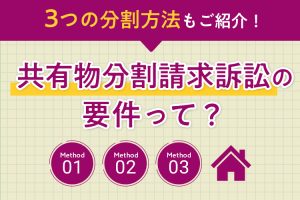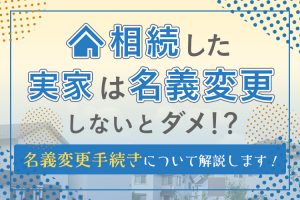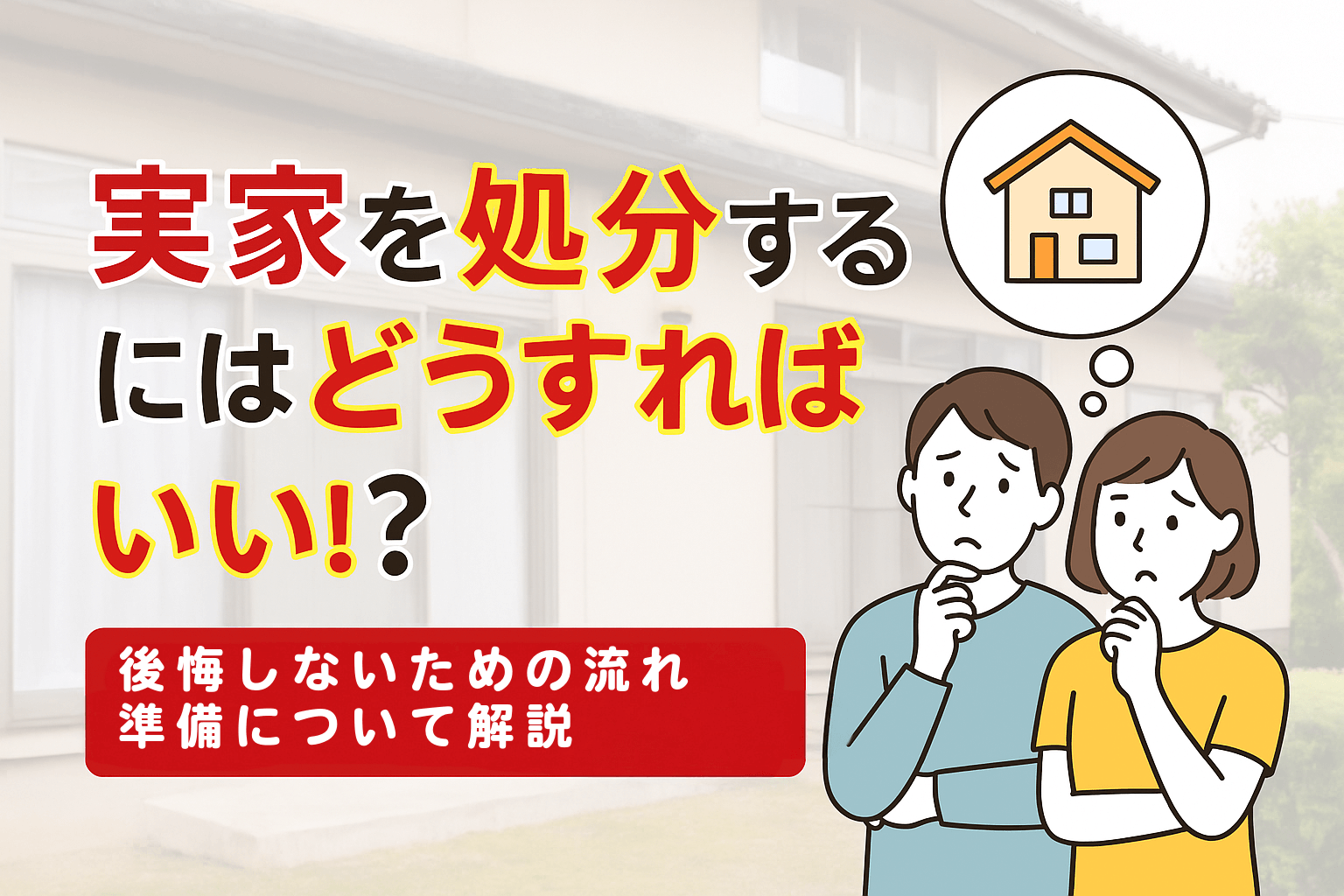
実家の処分を検討しているものの、どのように進めればよいのか分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
思い出が詰まった家だからこそ簡単には決断できず、空き家の状態で放置してしまうケースも多く見受けられます。
しかし、空き家を放置すると、建物の老朽化による倒壊リスクや空き巣、放火などの犯罪被害、さらには近隣トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、実家の処分方法からスムーズに売却するための具体的な流れ、放置することで起こり得るリスクについて解説します。
実家を手放すかどうか迷っている方や、処分する手順について知りたい方はぜひ参考にしてください。
- 実家を処分するベストな方法について
- 実家を処分する流れについて
- 実家を処分しないと発生する問題について

監修者
松屋不動産販売株式会社
代表取締役 佐伯 慶智
住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より松屋不動産販売株式会社にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。
実家を相続し処分したい人のベストな方法
相続した実家を処分したい人が取るべき方法は大きく3つあります。
- 使用する人がいない場合は売却を行う
- すぐに売却予定がない場合は賃貸に出す
- 空き家バンクに登録する
相続した実家を放置すると、維持費がかかったり近隣トラブルにつながるリスクもあるため注意が必要です。
このような問題を未然に防ぐために、できるだけ早めに実家の処分や活用方法を検討しましょう。
ここでは3つの処分方法について具体的に紹介します。
使用する人がいない場合は売却を行う
相続した実家に誰も住む予定がない場合は、売却を検討しましょう。
住宅は空き家の状態であっても、固定資産税や都市計画税、火災保険料などの維持費が発生します。
長期間にわたって使われないまま放置されると、経済的な負担が大きくなる一方です。また定期的な換気や清掃、庭木の手入れなど、管理も必要になります。
さらに誰も住んでいない住宅は劣化のスピードが早く、雨漏りや配管の破損、外壁の剥がれといった不具合が生じやすくなります。
状態が良いうちに売却することで、高く売れる可能性が高く、余計なコストをかけずに現金化することができるでしょう。
すぐに売却予定がない場合は賃貸に出す
相続した実家をすぐに売却するのが難しい場合や、将来的に自分や家族が住む可能性がある場合には、賃貸として活用するのも一つの選択肢です。
誰も住んでいない状態で維持し続けるよりも、家賃収入を得ながら管理費や固定資産税をまかなえるため、経済的なメリットがあります。
まずは不動産業者や管理会社に相談し、賃料の査定や募集条件の設定、入居者募集のアドバイスを受けましょう。
築年数が古い物件や設備が劣化している場合には、快適な住環境を提供するためのリフォームが必要になることもあります。
さらに、いずれ自分たちが住む予定がある場合は、契約期間を限定する「定期借家契約」を選ぶと、将来的に確実に退去してもらえるため安心です。
長期的な視点で、柔軟な活用方法を検討しましょう。
参考:定期借家制度|国土交通省
空き家バンクに登録する
売却や賃貸が難しい場合には、「空き家バンク」への登録を検討してみるのも一つの方法です。
空き家バンクとは、自治体が運営する空き家や空き地のマッチングサービスで、空き家を利活用したい人と、手放したい人とを結びつける仕組みです。
特に地方では、移住希望者や二拠点生活を考える人などの需要があり、意外と早く借り手や買い手が見つかるケースもあります。
登録にかかる費用はほとんどなく、自治体が関与している点でも安心です。
自治体によっては登録物件に対して補助金制度やリフォーム費用の一部支援など、魅力的なサポートが用意されているケースもあります。
ただし登録条件やサポート内容は自治体ごとに異なるため、事前に公式サイトなどで詳細を確認しましょう。
実家を処分する流れ
実家を処分するには、複数の手続きや準備が必要です。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割をする
- 実家の名義変更を行う
- 複数の不動産仲介業者に査定を依頼する
- 不動産仲介業者と媒介契約を締結する
- 買主が見つかったら売買契約を締結する
- 実家の売買代金の支払いと引き渡しを行う
相続した不動産をそのまま売却できるわけではなく、まずは法的な手続きをしっかりと踏まなければなりません。
特に相続に関する手続きは、順序を間違えるとトラブルの原因になるため注意が必要です。
ここでは、実家を売却する際の流れを解説します。
1.遺言書の有無を確認する
相続発生後、まずは遺言の有無を確認しましょう。
遺言書が残されていれば、内容に従って相続の手続きを進めることができるため、遺産分割がスムーズに行えます。
反対に、遺言書がない場合は相続人全員で協議を行う必要があり、手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書には以下の3種類があり、それぞれに特徴があります。
- 自筆証書遺言
すべてを自分で手書きして作成する形式で、手軽に行えるのが特徴ですが、書式に不備があると無効になる恐れがあります。現在は法務局で保管できる制度も整っており、法務局で保管することで紛失や改ざんのリスクを減らせます。 - 秘密証書遺言
内容を誰にも知られずに作成・保管できる遺言書です。手続きに手間がかかったり、内容が法的に有効かどうか不安が残る点もあることから、年間で100件程しか利用されていません。他の方法がある中で、あえて秘密証書遺言を選択するケースは稀でしょう。 - 公正証書遺言
公証人が関与して作成され、法的な不備がなく信頼性が最も高い形式です。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、相続時にもスムーズに手続きを進めやすくなります。
このように、遺言書の種類によって扱いやすさや信頼性に差があるため、それぞれの特徴を理解したうえで確認することが大切です。
参考:政府広報オンライン|知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
2.遺産分割をする
遺言書が存在しない場合や、記載内容があいまいで相続内容が明確でない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
不動産を誰がどのように相続するかを決めるためには、相続人同士が話し合い、合意に基づいた分割方法を選ぶことが重要です。
不動産の分け方には、以下の3つの代表的な方法があります。
- 実物分割
不動産が複数ある場合、それぞれの相続人が物件を分けて所有する方法です。ただし相続財産が実家のみの場合は、物理的に分けることができないため、実際にはあまり採用されない傾向にあります。 - 代償分割
1人の相続人が実家を相続し、その代わりに他の相続人へ、相続分に見合う現金(代償金)を支払う方法です。実家を誰かがそのまま住み続ける、あるいは管理していく場合に適しています。 - 換価分割
実家を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。相続人の誰も実家に住む予定がない場合や、平等な分配を希望する場合によく利用されます。
いずれの分割方法でも、話し合いの内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印を行う必要があります。
遺産分割協議書があることで、後々のトラブルを防ぎ、名義変更などの手続きも円滑に進めることができます。
参考:法務省|不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
3.実家の名義変更を行う
遺産分割が完了したら、名義変更の手続き(相続登記)を行います。
不動産の名義が故人のままでは、売却や譲渡、活用などの権利を正しく行使することができません。また名義が曖昧なまま放置していると、後になって相続人同士の間で所有権を巡るトラブルが発生するリスクもあります。
例えば、一部の相続人が勝手に売却を進めたり、別の相続人が所有権を主張したりするケースもあるため、早めに手続きを行うことが重要です。
さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので注意しましょう。
名義変更には主に以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 固定資産税明細書
- 不動産の登記事項証明書
- 相続人のうち新たな所有者の住民票
相続登記は専門知識のある司法書士に依頼するのが一般的で、ミスなく確実に進めるためにも安心です。
相続登記が完了すれば、ようやく不動産の売却や活用に向けた次のステップへ進むことができます。
4.遺品整理や不用品の処分をする
名義変更の手続きが完了したら、実家に残された遺品や不用品の整理をします。
相続した実家には、家具や家電、衣類、書類など、故人が生前使用していた多くの品が残されていることが一般的ですが、遺品や不用品を仕分けて処分するには大きな労力と時間を要します。
また思い出の詰まった品々を前にすると、感情的な負担が重なり、なかなか整理が進まないという方も多いでしょう。
上記のような場合には、遺品整理の専門業者に依頼する選択肢もあります。
プロの業者であれば、必要なものと不要なものを丁寧に仕分け、迅速に作業を進めてくれます。
遺品の供養や形見分けに対応してくれる業者もあり、精神的な負担を軽減しながら安心して任せることが可能です。
整理と処分が完了すれば室内が片付き、不動産の売却に向けた内覧対応やリフォーム準備もスムーズに進めやすくなります。
5.複数の不動産仲介業者に査定を依頼する
遺品整理が終わり室内の片付けが済んだら、実家の売却に向けて不動産業者へ査定を依頼しましょう。
不動産の査定には大きく以下の2種類があります。
- 簡易査定
所在地や土地面積、過去の取引事例などをもとに、机上でおおよその価格を算出する方法です。短時間で結果がわかるのがメリットです。 - 訪問査定
担当者が実際に物件を訪れて、建物の状態や周辺環境、日当たり、接道状況などを総合的に確認し、現実的な価格を提示してくれます。
まずは簡易査定で相場を把握し、売却の方向性を検討するとよいでしょう。
ただし査定額は不動産業者によって差が出ることが多いため、最低でも3社以上に依頼して比較検討することをおすすめします。
価格だけでなく、営業担当者の対応や提案力、地域での実績も見極めたうえで、信頼できる業者を選びましょう。
6.不動産仲介業者と媒介契約を締結する
査定結果を比較し、不動産業者を選んだら、売却活動を進めるために媒介契約を結びます。
媒介契約には、以下の3つの種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
それぞれの違いは以下の通りです。
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 他業者への仲介依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引(自分で入居者を見つけた場合の直接契約) | 可能 | 可能 | 不可 |
| 募集状況の報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズへの登録期限 | 登録義務なし | 契約締結後7営業日以内 | 契約締結後5営業日以内 |
| 契約期間の上限 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
一般媒介契約は、複数の不動産業者と同時に契約できる自由度の高い形式で、自分自身で買主を見つけることも可能です。ただし不動産業者ごとに販売活動への取り組みに差が出る場合もあります。
専任媒介契約は、1社のみに販売を依頼する代わりに、自分でも買主を探すことができる契約で、一般媒介契約と違って進捗状況の報告義務もあるため、意欲的な販売活動が期待できます。
専属専任媒介契約も1社との契約ですが、自分で買主を見つけることはできません。その代わり、不動産業者がより積極的に販売活動を行い、頻繁な状況報告が義務付けられているのが特徴です。
どの契約にもメリット・デメリットがあるため「どのくらい早く売却したいか」「どの程度売却活動に関われるか」といった観点から判断するとよいでしょう。
7.買主が見つかったら売買契約を締結する
不動産業者の仲介によって買主が見つかり、価格や条件に双方が合意すれば、売買契約を締結します。
売買契約とは、売主と買主の間で不動産の売買に関する内容を正式に書面で取り交わす重要な手続きです。
<p契約書には、売買価格、支払い方法、引き渡し日、手付金の金額、違約金の取り扱いなど、さまざまな条件が細かく記載されています。
<p契約内容を十分に確認し、納得したうえで署名・押印を行いましょう。
契約時には、不動産業者が作成する「重要事項説明書」に基づき、物件の権利関係や法的な制限、現況などの説明も行われます。
不明点があれば、その場で必ず確認することが大切です。
あとから「知らなかった」では済まないトラブルに発展する可能性もあるため、納得いくまで説明を受けておきましょう。
8.実家の売買代金の支払いと引き渡しを行う
売買契約が締結された後は、残代金の支払いと物件の引き渡しを行います。
通常は金融機関で決済を行い、買主が売買代金の残金を支払い、売主がその受領を確認したうえで鍵を引き渡す流れとなります。
同時に、司法書士によって所有権移転登記の手続きが進められ、正式に物件の名義が買主に変更されます。これらの流れにより、不動産取引としては一通りの手続きが完了します。
その後、万が一設備の不具合や事前の合意と異なる点があれば、補修対応や費用分担について協議が必要になります。
また水道・電気・ガスなどの公共料金の清算や、郵便物の転送手続きなどの細かな事務も忘れずに対応しましょう。
手続きがすべてが無事に完了すれば、実家の売却は正式に完了となります。
実家を処分しないと発生する問題
相続した実家をそのまま放置していると、時間の経過とともにトラブルが発生するリスクが高まります。
家は人が住まなくなると劣化が進み、防犯や近隣トラブル、さらには法的な問題にもつながる恐れがあります。
ここでは実家を処分せずに放置することで起こり得る代表的な問題を詳しく解説します。
建物の老朽化が進み倒壊の危険性が高まる
空き家を長期間放置していると、建物の劣化が進む要因になります。
雨漏りや木材の腐食、シロアリの被害などが起こりやすくなり、やがて屋根や外壁が崩れるなど、倒壊の危険性が高まります。
被害が周囲に及んだ場合、隣家や通行人に損害を与える可能性があり、所有者が損害賠償を求められるケースもあります。
実際に、倒壊した家屋の瓦礫が隣家の車を傷つけたり、通行人にケガをさせたりする事例も報告されています。
このようなリスクを防ぐために、相続した実家は早めに処分するのがおすすめです。
空き家の状態を放置することで空き巣犯のターゲットとして狙われる可能性がある
空き家は人の出入りがなく、夜間も照明が点かないため、防犯面で非常に弱い状態になります。
空き巣や不法侵入の標的となりやすく、窓を割って侵入されたり、家具・家電を盗まれたりといった被害が発生するリスクが高まります。
さらに荒らされた室内の修繕が必要になることもあり、精神的・経済的にも大きな負担となります。
特に人通りの少ない地域や、郊外にある空き家においては、人目につきにくいことからより狙われやすくなります。
防犯カメラの設置や定期的な見回りといった対策もありますが、維持コストがかかるため現実的に難しいケースが多いでしょう。
実家を長い間放置すると浮浪者にも住み着かれてしまう可能性がある
管理が行き届いていない空き家は、浮浪者や野生動物にとって都合の良い「住みか」となってしまうことがあります。
一度住み着かれてしまうと、自力での対応は難しく、法的手続きや専門業者の介入が必要になる場合もあり、費用や時間の負担がかかります。
さらに室内で火を使われるなどの危険な行為が行われれば、火災や近隣トラブルの原因にもなりかねません。
気づかないうちに近隣住民からの苦情が寄せられることもあります。
放火の被害に遭う危険性が高い
空き家は管理がされていない分、放火の標的になるリスクも高まります。
人気がない場所や周囲から死角になりやすい空き家は、放火犯に狙われやすく、一度火災が発生すると近隣住宅を巻き込む大惨事につながることもあります。
さらに空き家状態で火災が起きた場合、火災保険の適用条件を満たさない可能性があり、修繕費用や被害補償をすべて自己負担しなければならないケースもあります。
また火災による損害が第三者に及んだ場合は、所有者に法的責任が問われる可能性もあるため、深刻なリスクとして認識しておきましょう。
樹木が成長して隣家の敷地にまで侵入してしまう
空き家の敷地内にある庭木や雑草が、管理されないまま成長してしまうと、隣家の敷地にまで侵入してしまうことがあります。
草木の侵入により、近隣住民から「草木の枝が伸びてきて困る」といった苦情が寄せられることになり、関係が悪化する原因にもなります。
また放置された草木の状態によっては、撤去のために業者を呼ぶ必要があるため、除去費用や手配の手間もかかります。
放置すると相続人が増えてトラブルが発生しやすくなる
実家を長期間放置していると、相続人の数が増えてしまい、手続きがより複雑になる恐れがあります。
例えば、相続人の一人が亡くなれば、その配偶者や子どもが新たな相続人となり、相続関係が一気に複雑化します。
相続人が増えることで意見がまとまらず、遺産分割協議が長引いたり、処分のタイミングを逃してしまうケースもあります。
最悪の場合「誰も使わないが手放すこともできない不動産」となり、負の資産になってしまうこともあるでしょう。
将来的なトラブルを防ぐためにも、できるだけ早めに方向性を決めておくことが重要です。
まとめ
相続した実家をそのまま放置していると、建物の老朽化による倒壊リスクや空き巣・放火などの犯罪被害、近隣トラブル、さらには相続人間の争いといった深刻な問題に発展する可能性があります。
「今は使っていないから」「いつか考えればいい」といった判断で先延ばしにすると、気づかぬうちに大きな負担や責任を抱えることになりかねません。
実家の処分には、遺言書の確認や遺産分割協議、名義変更といった複雑な手続きが必要ですが、順序を踏んで進めれば着実に整理ができます。
売却、賃貸、空き家バンクなどの活用方法を含め、自分や家族にとって最適な選択肢を見つけることが大切です。
大切な実家だからこそ、放置せずにしっかりと向き合い、後悔のない形で整理・活用していきましょう。