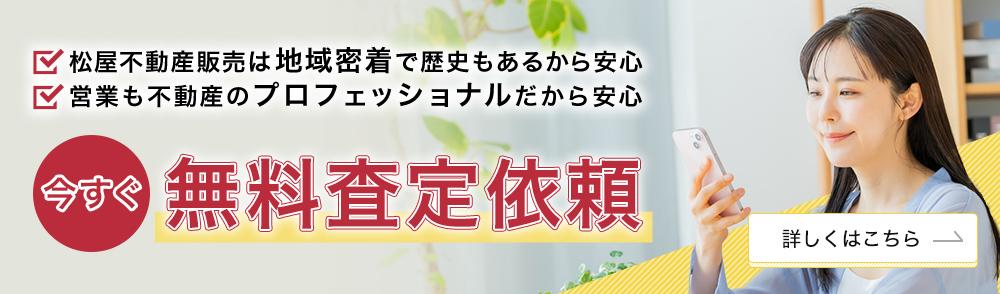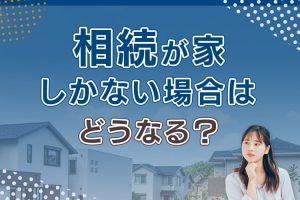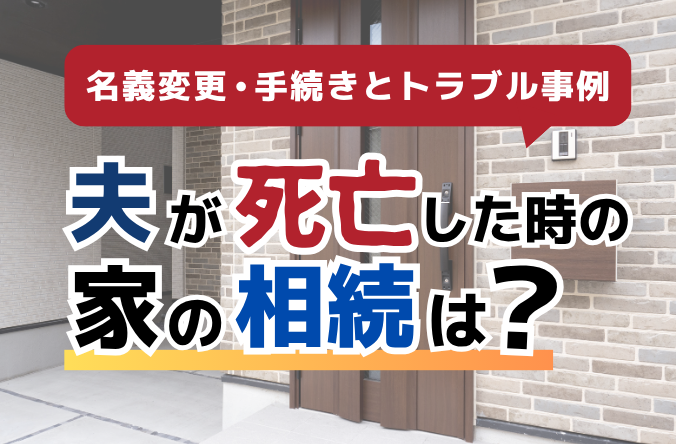
「夫が死亡したとき家を相続するには?」
「家の名義変更はいつまで?」
配偶者を亡くされて、突然の出来事に戸惑っている方は多いのではないでしょうか。
相続手続きや税金のことなど、何をどう進めればいいのか分からず、不安な気持ちを抱えている方は少なくありません。
家の相続は、配偶者や子どもをはじめとする法定相続人の間で行われます。
相続人の範囲や相続分は、家族構成や遺言の有無によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。
本記事では、夫が亡くなった際に家の相続人となる人の範囲や、配偶者居住権といった重要な制度、相続手続きの流れ、相続税の計算方法など、幅広く解説しています。
相続手続きは後回しにすると、家族間のトラブルや資産の凍結につながる恐れがあるので、正しい知識を理解し、安心して手続きを進めていきましょう。
本記事でわかることは以下の通りです。
この記事でわかること
-
夫が死亡したときに家を相続できるのは誰?
-
夫死亡時に住宅ローンが残っている家の相続はどうなる?
-
夫が死亡した際の家の相続税の計算方法
-
夫が死亡した場合の配偶者居住権とは?
-
夫が死亡した後の家の相続手続きの流れ
-
夫死亡後に家を相続したと際によくあるトラブル事例

監修者
松屋不動産販売株式会社
代表取締役 佐伯 慶智
住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。
目次
夫が死亡したときに家を相続できるのは誰?
家の相続人は、基本的に法律で定められた「法定相続人」が対象です。
相続人となる範囲や順位は、被相続人(亡くなった夫)の家族構成によって異なります。
まず大切にされるべきは被相続人の意思ですが、遺言で法定相続人を外そうとしても、「遺留分の請求」があるため、完全に相続させないことはできません。
また、配偶者と子どもがいる場合は、共同で財産を相続することが一般的ですが、子どもがいない場合や、すでに他界している場合などは、親や兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。
遺産分割では、法定相続分を基準とした協議が求められ、相続人の間で合意が必要です。
事前に関係者を確認しておかないと、のちのトラブルに発展する恐れがあります。
以下で相続人の範囲や相続割合について詳しく解説します。
家の相続人は配偶者・子どもが一般的
被相続人である夫に配偶者(妻)と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもです。
配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合はその子どもと一緒に財産を分け合う形になります。
なお、子どもがすでに亡くなっている場合、その子(孫など)が代襲相続することになります。
ただし、家族構成によっては他の親族が相続人になることもあるため、誰が相続権を持つかを正確に確認することが大切です。
法定相続人の順位と相続割合
法定相続人の範囲と順位は民法で定められており、以下のような優先順位があります。
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属(父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、順位ごとの親族と共同で相続する形になります。
相続割合は以下のとおりです。

例えば、子どもがいない場合は親と、親もすでに亡くなっていれば兄弟姉妹と遺産を分け合うことになります。
相続割合は、配偶者と子どもなら配偶者2分の1、子ども2分の1となります。
配偶者と親(父母)なら配偶者3分の2と親3分の1の割合です。
配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3と兄弟姉妹4分の1が基本的な分配比率です。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されるため、事前に有無を確認することが重要です。
夫死亡時に住宅ローンが残っている家の相続はどうなる?
住宅ローンが残っている状態で夫が亡くなった場合、確認すべきポイントは以下の通りです。
- 団体信用生命保険に加入時は返済が免除になる
- 団体信用生命保険が適用できないケース
- 住宅ローンの残債が返済できない場合の手続き
原則として、家を相続すればローン債務も引き継ぐことになりますが、「団体信用生命保険」に加入していたかどうかが重要な判断材料となります。
団体信用生命保険により残債が完済されるケースもあれば、適用外で返済が必要になるケースもあります。
団体信用生命保険の仕組み、万が一ローンを返済できない場合の対応策まで詳しく解説します。
団体信用生命保険に加入時は返済が免除になる
団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害になったときに、残っているローンを保険金で完済できる仕組みです。
夫が団体信用生命保険に加入していた場合、その死亡が保険の対象条件に該当すれば、ローン残債はすべて免除されます。
つまり、妻や家族は追加の返済義務を負わずに、家を相続してそのまま住み続けることが可能です。
ローンの支払いが免除されることで、相続後の生活再建にも大きな安心材料となります。
団体信用生命保険の加入有無は、住宅ローン契約時の書類やローンを借り入れた金融機関に確認すれば把握できます。
特に民間銀行の住宅ローンでは加入が義務付けられていることが多いですが、フラット35などの公的ローンでは加入が任意になっているケースもあります。
保障内容も契約によって異なるため、一般団体信用生命保険だけでなく三大疾病特約やがん特約などのプラン別に、補償範囲と支払い条件を確認しておくことが重要です。
団体信用生命保険が適用できないケース
団体信用生命保険に加入していても、必ずしも保険金が支払われるとは限りません。
例えば、加入時に健康状態に関する虚偽の申告があった場合(告知義務違反)や、契約内容が限定保障型で死亡原因が対象外だった場合など、保険金の支払いが拒否されることがあります。
さらに、長期延滞によって契約が失効していた場合にも、保険金は支払われません。
契約者が正しく管理していなかった場合、残された家族が思わぬ返済負担を負うリスクもあるため注意が必要です。
また、契約時のプランによっては、保障開始までの待機期間が設定されていることもあります。
夫がローン契約後すぐに死亡したようなケースでは、団体信用生命保険の保障が開始前だったという事例も少なくありません。
団体信用生命保険の適用可否は、死亡時点の契約状態や保険の種類によって判断されるため、ローン契約時の資料をよく確認し、疑問がある場合は金融機関や保険会社へ早急に問い合わせることが大切です。
住宅ローンの残債が返済できない場合の手続き
住宅ローンが残っている状態で夫が亡くなり、団体信用生命保険の保障も受けられなかった場合、家を引き継ぐ相続人は原則としてローン債務も含めて相続することになります。
しかし、相続人が返済を継続できない場合には、早急な対応が必要です。
選択肢としては、相続自体を放棄する方法や、家を売却してローンを清算する方法、あるいは金融機関と返済条件の見直しを協議する方法などが挙げられます。
相続放棄は家庭裁判所に申述する手続きが必要で、相続開始(死亡を知った日)から3か月以内という期限があります。
この期間を過ぎると相続を承認したとみなされるため注意が必要です。
また、相続人が複数いる場合は、放棄の意思を全員で統一することが望ましいでしょう。
任意売却による清算を選ぶ場合は、ローン残債より売却価格が下回る可能性もあるため、金融機関との調整や専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
夫が死亡した際の家の相続税の計算方法
家を相続した場合、その不動産の評価額や遺産全体の額に応じて、相続税が課される可能性があります。
相続税は「取得した財産の評価額」から「基礎控除」や「各種特例」を差し引いた金額に対して課税される仕組みです。
被相続人が所有していた不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額をもとに計算されるのが一般的です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、妻と子ども1人が相続人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
この範囲内に家や預貯金などの遺産総額が収まる場合は、相続税がかからないこともあります。
また、配偶者には「配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)」が適用されるため、妻が多くの財産を相続しても税負担が生じないケースが多くあります。
さらに、居住用不動産に対する「小規模宅地等の特例」を適用すれば、土地の評価額を最大80%まで減額できる場合もあります。
ただし、この特例を受けるには、相続人がその家に引き続き住むなど一定の条件があるため、適用要件の確認が必要です。
相続税の有無は、遺産の総額・構成・家族構成によって異なるため、正確な計算には税理士への相談が推奨されます。
夫が死亡した場合の配偶者居住権とは?
偶者居住権とは、夫が亡くなったあとも、妻が亡夫名義の家に住み続けられるようにするための法的制度です。
2020年4月に施行された制度で、相続財産を公平に分けながらも、配偶者の生活を安定させることを目的としています。
制度の概要と適用条件について詳しく解説します。
制度の概要と適用条件
配偶者居住権とは、亡くなった夫が所有していた建物に、残された配偶者が無償で住み続けられる権利のことです。
遺産分割協議や遺言で明記されていれば設定でき、登記することで第三者に対しても効力が生じます。
適用には「夫の死亡時に実際にその家に住んでいたこと」や「遺産分割や家庭裁判所の審判で認められたこと」などの要件が必要です。
この制度は、不動産の評価額を抑えつつ居住の安定を図れる点でメリットがあります。
配偶者居住権と所有権を別々に分けて相続するため、家そのものの所有は子どもが引き継ぎ、妻は住み続けるといった柔軟な分割が可能です。
特に相続財産に占める不動産の割合が大きい場合に有効とされます。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は一見メリットが大きいように思えますが、いくつかの注意点もあります。
まず、配偶者が自宅を「売る・貸す」といった処分はできません。
居住権はあくまで住み続ける権利であり、経済的な活用は制限されます。
また、配偶者が亡くなった時点でこの権利は消滅し、子どもなどの相続人には引き継がれません。
さらに、不動産全体の所有者が別に存在することから、修繕や建て替えの判断が複雑になりやすく、所有者との協議が必要になる場面もあります。
加えて、登記が必須となるため、手続きに手間や費用がかかる点にも留意が必要です。
制度を活用する際は、実際のライフプランや財産構成に応じて、司法書士や税理士に相談することが推奨されます。
夫が死亡した後の家の相続手続きの流れ
夫が死亡した際に必要な家の相続手続きは以下の通りです。
家の相続手続きの基本的な流れ
- 夫の戸籍謄本や必要書類の取得
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人の確定と遺産分割協議
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続登記(名義変更)の手続きを法務局で行う
配偶者を亡くした直後は、気持ちの整理もつかない中で多くの手続きを進めなければならず、不安や戸惑いを感じる方も少なくありません。
下記では、家の相続に必要な基本の流れをわかりやすく解説します。
【STEP1】夫の戸籍謄本や必要書類の取得
まず最初に行うべきことは、相続手続きに必要となる書類の収集です。
誰が法定相続人であるかを確認するために必要で、市区町村役場で申請して取得します。
相続手続きで必要となる主な書類の一覧は以下のとおりです。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 亡夫の戸籍謄本(出生〜死亡まで) | 夫の本籍地の市区町村役場 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 夫の本籍地の市区町村役場 |
| 住民票(除票) | 最後に住んでいた市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の住民票または印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 夫名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局 |
役所の窓口で取得する場合は、身分証や印鑑を持参し、事前に電話で必要書類を確認しておくとスムーズです。
【STEP2】遺言書の有無を確認する
遺産相続において、遺言書の有無は非常に重要なポイントです。
遺言書があるかどうかによって、その後の手続きや相続の方法が大きく変わります。
まずは故人が遺言を残していなかったか、しっかりと確認しましょう。
遺言書には主に次の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人がすべての内容を自分の手で書き、日付と氏名を記し、押印して作成する遺言書の形式です。
費用をかけずに自分一人で作成できるため、もっとも手軽な遺言の方法として広く利用されています。
ただし、法律で定められた形式に従っていないと無効になる恐れがあるため、注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与し、法的に確実な形で作成される遺言書のことです。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が内容を文書にまとめて作成します。
証人2名の立ち会いも必要で、遺言の内容や手続きが法律に適合しているかを公証人が確認するため、形式不備などによって無効になるリスクが非常に低いのが大きな特徴です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が内容を誰にも見せずに作成できる、もっとも「秘密性」が高い遺言の形式です。
遺言者自身があらかじめ遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持ち込み、公証人と証人2名の立ち会いのもと「これは自分の遺言書である」と申述することで手続きを行います。
公証人は内容には関与せず、あくまで「遺言書が確かに提出された」という事実を公文書にして残すだけです。
【STEP3】相続人の確定と遺産分割協議
相続手続きを進めるうえで重要なステップのひとつが、「誰が相続人なのか」を明確にすることです。
亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認し、配偶者や子ども、場合によっては親や兄弟姉妹といった法定相続人を確定させます。
相続人が確定したら、次に行うのが「遺産分割協議」です。これは、相続人全員で話し合い、遺産(不動産・預金・株式など)をどのように分けるかを決める手続きです。
話し合いがまとまれば、内容を文書にまとめて「遺産分割協議書」として残す必要があります。
なお、相続人全員が署名・押印しなければ協議は成立しません。
【STEP4】遺産分割協議書を作成する
相続人全員の話し合いで遺産の分け方が決まったら、内容を正式に文書にまとめ「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
作成にあたってのポイントは以下のとおりです。
- 相続人全員の合意が必要
- 取得する財産を具体的に記載する
- 相続人全員が署名・実印で押印する
- 複数部作成し、相続人それぞれが保管する
遺産分割協議書は、家や土地などの相続登記に必要不可欠な書類です。
将来のトラブルを防ぐためにも、正確かつ丁寧に作成しましょう。
【STEP5】相続登記(名義変更)の手続きを法務局で行う
相続人の間で遺産の分割が決まり、遺産分割協議書が完成したら、次に行うのが「相続登記」です。
相続登記は亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きで、法務局で行います。
相続登記は、2024年4月からは義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
不動産の所在地を管轄する法務局に申請し、問題がなければ数日から数週間で名義が変更されます。
夫死亡後に家を相続したと際によくあるトラブル事例
夫が死亡し、家を相続したときによくあるトラブル事例を3つ紹介します。
- 相続人が複数いる場合における財産の分割
- 相続不動産の利用について意見が合わない
- 共有名義にすることで相続権が複雑化する
夫が亡くなり、自宅などの不動産を相続することになった際、思わぬトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。
トラブル事例を知り、事前に避けられるリスクについて考えましょう。
相続人が複数いる場合における財産の分割
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかでトラブルにつながりやすいです。
法律で定められた法定相続分に従う方法もありますが、多くの場合は相続人同士で話し合い、「誰が何を受け取るか」を協議して決める必要があります。
不動産、預貯金、株式などさまざまな資産がある場合は、それぞれの価値を踏まえて公平に分配することが求められます。
協議が円滑に進まない場合は、家庭裁判所での調停に発展することもあり、早期の合意形成が重要です。
相続不動産の利用について意見が合わない
相続財産に不動産が含まれる場合、その活用方法を巡って相続人間で意見が食い違うことがあります。
たとえば、「売却して現金化したい」という意見と、「残して住み続けたい」という意見が対立することも珍しくありません。
不動産は簡単に分けられない資産であるため、利用方法についての合意形成が特に難しい傾向があります。
実際の使用予定や各相続人の生活状況を考慮しながら、冷静に話し合うことが求められます。
共有名義にすることで相続権が複雑化する
話し合いの結果、不動産を複数の相続人で共有名義にすることがありますが、注意が必要です。
共有名義にすると、売却や建て替えなどの意思決定を行う際に、共有者全員の同意が必要になります。
将来的に一部の共有者が行方不明になったり、意見がまとまらなかったりすると、不動産の活用や処分が困難になります。
また、次の世代に相続が繰り返されることで、権利関係がさらに複雑化し、手続きに時間と費用がかかるケースもあるでしょう。
初めから単独名義にすることも、選択肢として検討する価値があります。
夫死亡後の家の相続手続きが不安な方は松屋不動産販売にお任せ!
相続は人生の中でも慣れない手続きのひとつであり、とくに不動産が絡むと「何から始めればいいのか分からない」「親族間の調整が不安」といった悩みを抱える方が少なくありません。
松屋不動産販売では、経験豊富なスタッフが士業と連携し、一貫してサポートいたします。
地域密着型ならではの細やかな対応で、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をご用意しております。
無料相談・査定も随時受け付けているので、不安な気持ちを安心に変えるために、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
夫が亡くなった後の家の相続は、法律や制度、家族間の事情が複雑に絡み合うため、冷静な対応が必要です。
家の名義変更(相続登記)をはじめとする相続手続きは、戸籍謄本や遺言書の確認、相続人の確定、遺産分割協議など、順を追って進める必要があります。
さらに、相続人同士で不動産の使い道を巡る意見の対立など、トラブルに繋がる可能性もあります。
相続は大切な財産と家族の関係に関わる一大事です。
悩んだときはひとりで抱え込まず、信頼できる専門家に相談しながら、安心・円満な相続を目指して進めていきましょう。